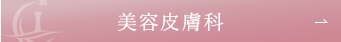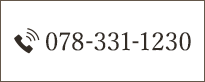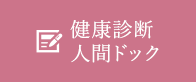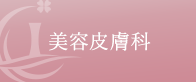潰瘍性大腸炎とは
 腸の炎症によってさまざまな症状をきたす疾患の総称を「炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)」といいます。そして代表的な炎症性腸疾患として、「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」が挙げられます。
腸の炎症によってさまざまな症状をきたす疾患の総称を「炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)」といいます。そして代表的な炎症性腸疾患として、「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」が挙げられます。
どちらもはっきりとした原因が解明されておらず、根治治療も未確立であることから、厚生労働省より難病の指定を受けています。ただ、適切な治療によって寛解の状態を維持し、以前とほぼ変わらない生活を取り戻すことが可能です。また難病として、一定の要件を満たした場合には医療費の補助が受けられます。
潰瘍性大腸炎では、大腸の連続的な炎症によって腹痛・下痢・粘血便といった症状が引き起こされます。潰瘍性大腸炎は病変の拡がりや経過などにより下記のように分類されます。
潰瘍性大腸炎の分類について
潰瘍性大腸炎は、症状の出方や病変の広がり方、重症度、経過の様子によっていくつかのタイプに分類されます。ここでは、それぞれの分類についてわかりやすくご紹介します。
病期による分類
活動期
血便や下痢などの目立つ症状がある時期です。
寛解期
症状が落ち着いている時期で、日常生活を普通に送ることができる状態です。
病変の範囲による分類
直腸炎型
病変が直腸のみにとどまっています。
左側大腸炎型
直腸から下行結腸(お腹の左側)まで病変が広がっています。
全大腸炎型
横行結腸よりもさらに奥(口側)まで病変が及んでいます。
重症度による分類
以下の6項目を総合的に評価して、軽症・中等症・重症に分類されます。
- 排便の回数
- 血便の程度
- 体温
- 脈拍
- ヘモグロビン(Hb)値
- 炎症の指標(赤沈またはCRP)
分類不能型
再燃寛解型
寛解と再燃(症状の再発)を繰り返すタイプです。
慢性持続型
症状が長期間続くタイプです。
急性劇症型
急激に症状が悪化し、重症化するタイプです。入院が必要な場合もあります。
初回発作型
初めて発症した時の状態です。
潰瘍性大腸炎の症状チェック

- 腹痛
- 下痢
- 血便、粘血便
潰瘍性大腸炎の主な症状は、上記の通りです。これらの症状が強く現れる時期と、鎮まる時期を繰り返す点が潰瘍性大腸炎の特徴です。
潰瘍性大腸炎の原因
はっきりとした原因は解明されていませんが、免疫の異常、食生活の乱れ、腸内細菌叢のバランスの乱れなどが影響しているものと思われます。
また、家族性も指摘されており、潰瘍性大腸炎の血縁者がいる人は、そうでない人と比べると潰瘍性大腸炎の発症リスクが高くなります。
潰瘍性大腸炎は、上記のような原因・リスクが複合的に影響し、発症するものと考えられます。
潰瘍性大腸炎の検査・診断
 問診では、症状、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお伺いします。
問診では、症状、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお伺いします。
その上で、大腸カメラ検査を行い、診断します。潰瘍性大腸炎では、大腸に連続的な炎症が認められます。また、似た症状を持つクローン病などとの鑑別のためにも、大腸カメラ検査は重要な検査となります。当クリニックでは、内視鏡の専門医・指導医である院長が、鎮静剤を使ったほとんど苦痛のない大腸カメラ検査を行っておりますので、安心してご相談いただけます。
その他、必要に応じて血液検査、腹部超音波検査なども行います。
潰瘍性大腸炎と
間違えやすい病気とは?
潰瘍性大腸炎とよく似た症状を持つ病気としては、クローン病、細菌性腸炎などがあります。
検査・診断においては、特にこれらの疾患との鑑別を慎重に行います。
クローン病
潰瘍性大腸炎と共に、炎症性腸疾患に分類される病気です。大腸・小腸を中心とした口~肛門までの消化管で、慢性的な炎症が起こります。大腸のみに炎症が留まる潰瘍性大腸炎とは区別して治療する必要があります。
クローン病では、腹痛、下痢、体重減少、血便、発熱、貧血、倦怠感といった症状が見られます。
カンピロバクター腸炎
カンピロバクターに汚染された食品を口にすることで発症する細菌性腸炎です。多くは鶏肉を原因として感染し、2~5日の潜伏期間を経て、下痢、高熱、腹痛、吐き気・嘔吐、頭痛などの症状が現れます。
サルモネラ腸炎
サルモネラ菌に汚染された食品を口にすることで発症する、細菌性腸炎です。主に鶏卵・肉類を原因として感染し、8時間から4日の潜伏期間を経て、吐き気・嘔吐、腹痛、下痢、発熱などの症状が現れます。
潰瘍性大腸炎の治療
潰瘍性大腸炎の診断後は、主に以下のような治療を行います。
潰瘍性大腸炎では活動期と寛解期が繰り返されます。治療では、完治ではなく寛解期を長期にわたって維持することが目的となります。
薬物療法
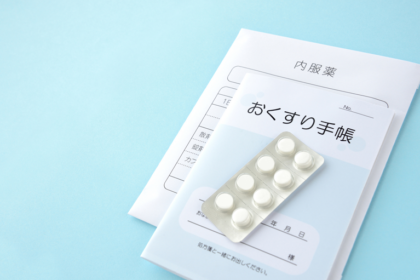 薬物療法の中心になるのは、潰瘍性大腸炎の治療薬として開発された5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤)です。内服・座薬・注腸により投与します。活性酸素やロイコトリエンといった炎症性物質を取り除く作用により、症状を改善します。
薬物療法の中心になるのは、潰瘍性大腸炎の治療薬として開発された5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤)です。内服・座薬・注腸により投与します。活性酸素やロイコトリエンといった炎症性物質を取り除く作用により、症状を改善します。
5-ASA製剤で十分な効果が得られない場合には、免疫調整薬、ステロイド、生物学的製剤、炎症性サイトカイン阻害薬などを使用することもあります。
薬剤によっては潜在性の感染症の憎悪をきたすことがあるため、事前にB型肝炎などの感染症の検査が必要となります。
重症例では入院が必要になることがあり、その場合は速やかに提携する病院をご紹介します。
生活習慣の改善
主に食生活の改善を行います。
ただ、寛解期には基本的にほとんど制限は生じません。活動期になった時に、速やかに寛解期へと移行させるための食事制限を行います。
詳しくは、次の項目をご覧ください。
潰瘍性大腸炎の食事
活動期と寛解期で、食事療法の内容が異なります。
活動期の食事療法
高エネルギー、高タンパク、低脂肪の食事を心がけます。また、食物繊維も摂り過ぎないようにしてください。
反対に、以下のような食品は控えます。
- 揚げ物、脂っこい物
- 香辛料
- 豆類、きのこ類、山菜類
- コーヒー、アルコール
- 冷たいもの
寛解期の食事療法
寛解期には、ほとんど食事制限はありません。暴飲暴食は避けつつ、バランスの良い食事を摂るようにしてください。
飲み物について
少なくとも活動期には、コーヒー、アルコール、キンキンに冷えた飲み物などを避けるようにしましょう。
寛解期も、ご自身の体質に合わせた調整を
寛解期には、基本的に食事制限はありません。
ただ、人によってはコーヒー、アルコール、牛乳、冷たい飲み物などが下痢の原因になることがあります。「寛解期だから何を飲んでも大丈夫」というわけではなく、ご自身の体質と相談しながら、摂り過ぎないことが大切です。
潰瘍性大腸炎のよくある質問
潰瘍性大腸炎とクローン病の共通点、
違いを教えてください。
炎症性腸疾患に分類されること、難病の指定を受けていること、腹痛・下痢・血便といった症状が見られることは、潰瘍性大腸炎とクローン病で共通しています。
違いとしては、潰瘍性大腸炎の炎症が大腸に留まるのに対して、クローン病では口~肛門の全消化管で炎症が起こり得るという点が挙げられます。ただ、クローン病の場合も多くは大腸・小腸で炎症が起こります。また炎症の程度については、クローン病の方が強く現れやすく、潰瘍になることも少なくありません。
潰瘍性大腸炎の合併症はありますか?
腸管で起こる合併症としては、潰瘍化に伴う大量出血、穿孔、中毒性巨大結腸症などが挙げられます。また潰瘍性大腸炎を長期にわたって放置していることで、大腸がんのリスクが高くなると言われています。
その他、腸管外においては、免疫システム不全、栄養状態低下といった合併症が見られます。これにより、関節炎や皮膚病変、膵炎、血栓塞栓症、原発性硬化性胆管炎、血管炎などが引き起こされることがあります。
寛解期にも、本当は厳しく食事制限を
した方がいいのでしょうか?
寛解期には、基本的に食事制限は必要ありません。寛解期に活動期のような厳しい食事制限を行うことで、ストレスやQOLの低下を招く可能性があるためです。また潰瘍性大腸炎は基本的に完治せず、長く付き合っていく病気です。そういった意味でも、寛解期にはストレスの少ない食事を摂ること、QOLを維持できる食事を摂ることが大切になります。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員