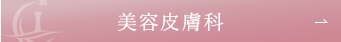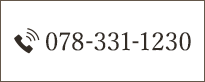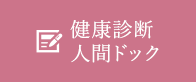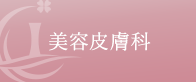- 朝・夜・自宅・病院など
異なる血圧の診断基準 - 高血圧症とは
- 高血圧症の原因
- 頭痛やめまいは高血圧のサイン?
- 高血圧を放置すると怖い!?
- 高血圧症の治療(血圧を下げる方法)
- 控えた方がいい食べ物とその理由
朝・夜・自宅・病院など
異なる血圧の診断基準
 日本高血圧学会においては、診察室血圧(病院やクリニックで測った血圧)の正常値を「120/80mmHg未満」、家庭血圧(ご家庭で測った血圧)の正常値を「115/75mmHg未満」と定めています。高血圧症の診断を行う場合には、診察室血圧、家庭血圧を測り、総合的に判断します。
日本高血圧学会においては、診察室血圧(病院やクリニックで測った血圧)の正常値を「120/80mmHg未満」、家庭血圧(ご家庭で測った血圧)の正常値を「115/75mmHg未満」と定めています。高血圧症の診断を行う場合には、診察室血圧、家庭血圧を測り、総合的に判断します。
なお、診察室血圧と家庭血圧の差が大きいケースでは、緊張の少ない家庭血圧の結果を優先して診断します。
診察室血圧
正常値は120/80mmHg未満となります。
診察室血圧を何度か測定し、最高血圧140mmHg以上、または最低血圧90mmHg以上である場合に高血圧と判定します。
診察室はご自宅よりもやや緊張が生じるため、いずれの基準もやや高めに設定されています。
白衣高血圧・仮面高血圧
家庭血圧が正常であり、診察室血圧が高血圧になることを、医師が着る白衣をなぞって「白衣高血圧」と言います。
一方で、診察室血圧が正常であり、家庭血圧が高くなることを「仮面高血圧」と呼びます。
家庭血圧
正常値は115/75mmHg未満となります。
ご自宅で連続5~7日測定した血圧の平均値を用います。最高血圧135mmHg以上、または最低血圧85mmHg以上である場合に高血圧と判定します。
早朝高血圧
早朝における家庭血圧が135/85mmHg以上である高血圧です。脳・心臓の血管疾患のリスクが高くなると言われています。
昼間高血圧
昼間における家庭血圧が135/85mmHg以上である高血圧です。仕事、あるいは家事などによるストレスに起因することが多くなります。
夜間高血圧
夜間における家庭血圧が120/70mmHg以上である高血圧です。脳・心臓の血管疾患のリスクが高くなると言われています。
ストレス性高血圧
仕事、家事、人間関係、介護、育児などによる肉体的・精神的ストレスを主な原因として起こる高血圧です。
ただ、血圧を測定する際には通常、これらのストレスが軽減・解消されていることも多いため、発見できないケースが少なくありません。
高血圧症とは
高血圧症とは、慢性的に血圧が高くなる病気です。血液が常に動脈の壁を押すことになるため、放置していると動脈硬化を進行させ、狭心症や心筋梗塞・脳卒中・腎臓病などの発症リスクを高めます。
高血圧症単独ではほとんど自覚症状がないため、医療機関やご家庭での血圧測定によって早期発見することが大切になります。
先述の通り、診察室血圧・家庭血圧を測定し、総合的に診断します。
高血圧症の原因
高血圧症は、大きく本態性高血圧症と二次性高血圧症に分けられ、それぞれ原因が異なります。
全体の90%以上を、本態性高血圧症が占めます。
本態性高血圧症
生活習慣の乱れを原因として起こる、いわゆる「生活習慣病」に分類される高血圧症です。主に、以下のような原因が挙げられます。
- 塩分の摂り過ぎ
- お酒の飲み過ぎ
- 肥満
- 運動不足
- 睡眠不足
- ストレス
- 生活リズムの乱れ
- 野菜・果物の不足
- 喫煙
- 加齢・遺伝
二次性高血圧症
腎臓疾患、内分泌疾患、睡眠時無呼吸症候群、脳血管障害・脳腫瘍、薬の副作用などの明らかな原因があり、その影響によって血圧が高くなる高血圧症です。
治療では、これら原因疾患の治療が行われます。
頭痛やめまいは
高血圧のサイン?
高血圧症と診断された場合にも、ほとんど自覚症状がありません。
稀に以下のような症状が認められることもありますが、患者様ご自身は「まさか高血圧が原因だとは思っていなかった」というケースが大半です。症状から高血圧を早期発見するのは難しく、それゆえに医療機関・ご自宅での血圧測定が大切になります。

- 頭痛
- めまい
- 動悸
- 肩こり
- 頭がボーっとする
高血圧を放置すると怖い!?
高血圧とは、動脈の内壁に慢性的に強い圧力がかかる病気です。自覚症状がほとんどないまま、血管がもろく硬くなる「動脈硬化」を進行させます。そして動脈硬化は、狭心症や心筋梗塞・脳卒中、腎臓疾患の発症リスクを高めます。
気づかないまま進行し、健康・命を危険にさらす、QOLを低下させる上記の疾患のリスクが上昇するところに、高血圧の怖さがあります。
高血圧症の治療
(血圧を下げる方法)
高血圧症の治療には、血圧を下げることを主な目的とした、以下のような方法があります。
食事療法
減塩
 食事療法においてもっとも大切なのが、塩分の摂取量を減らす減塩です。以下のような方法で、減塩に取り組みましょう。
食事療法においてもっとも大切なのが、塩分の摂取量を減らす減塩です。以下のような方法で、減塩に取り組みましょう。
- 味が濃く(塩分が多く)なりがちな外食を避け、自炊をする
- 調理の際には塩分(塩・しょうゆ・ソース等)の使用を少なめにする
- 塩分の多いレトルト食品、できあいの弁当・総菜はできるだけ避ける
- 主食はできるだけ白米を選び、塩分の多い麺類・パンを控える
- 塩分の代わりに天然出汁、スパイスを活用する
- しょうゆやソースは、料理に「かける」のではなく、皿に出して適量を「つける」
適正体重までの減量
肥満は高血圧症だけでなく、糖尿病や脂質異常症など他の生活習慣病の原因にもなります。
肥満の方は、食事療法と運動療法を組み合わせ、適正体重までのダイエットを図りましょう。食事を抜く等の無理なダイエットではなく、継続しやすい方法で、少しずつダイエットをすることが大切です。
適正体重は、以下の計算式で算出できます。
- 適正体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
たとえば身長が170cmであれば、「1.7×1.7×22」で計算し、標準体重は約63.5kgとなります。
※性別・筋肉量によっても、適正体重は変わってきます。具体的な目標体重は、医師と相談して決めましょう。
規則正しく3食を摂る
毎日、できるだけ決まった時間に3食を摂るようにしましょう。決まった時間に適正な量を摂ることで、空腹を感じにくくなり、間食も減らせます。
アルコールは控えめに
禁酒が理想的ですが、お酒が好きな人にとっては過度の制限はストレスとなります。
少なくとも、以下の範囲内での飲酒に留めましょう。
- 男性…1日あたり、日本酒であれば1合・ビール中瓶であれば1本・ワインであれば2杯弱以下
- 女性…1日あたり、日本酒であれば1/2合・ビール中瓶であれば1/2本・ワインであれば1杯弱以下
運動療法
運動は、血管の内皮機能を改善し、血圧を下げてくれます。
1日60分間の運動を週3回行う(または1日30分間の運動を毎日行う)ことで、収縮期血圧を20mmHg以上、拡張期血圧を10mmHg以上下げる効果が期待できます。
特に、以下のような有酸素運動がおすすめです。
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- 水泳、水中歩行
- サイクリング
薬物療法
食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合には、薬物療法を導入します。
使用するのは、血圧を下げる「降圧剤」です。降圧剤には、血管に直接作用するもの、心臓に働きかけ送り出す血液量を減らすもの、尿量を増やし血液量を減らすもの、自律神経に働きかけ血管の収縮を抑制するもの、血圧を上昇させる物質を減らすものなど、さまざまな種類があります。
控えた方がいい
食べ物とその理由
高血圧症の治療や予防において、控えるべき食品、その理由をご紹介します。
塩分が高いもの
- 外食全般
- できあいの弁当、総菜
- レトルト食品、インスタント食品
- 味の濃いもの
- しょうゆ、ソースのかかっているもの
- ドレッシング
- 漬物 など
理由
私たちの身体は、常に塩分濃度を一定に保とうとしています。塩分を摂り過ぎると、体内の塩分濃度を下げるために水分を溜め込みます。これにより心臓に送り込まれる血液量が増加し、血圧が高くなります。また、塩分の摂取によって交感神経が活発化することも、高血圧を招く原因となります。
アルコール
ビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーなどさまざまな種類がありますが、いずれも飲み過ぎは高血圧症、およびその他の生活習慣病の原因になります。
禁酒が理想的ですが、難しい(禁酒がストレスになる)という場合には、医師と相談した上で、その量を抑えるように努めましょう。
理由
アルコールには、血管を収縮させる作用、心臓の拍動を速める作用などがあります。また、アルコールを飲むことによって塩分・脂質の多い食事やおつまみを摂りがちになること、食事の栄養バランスが偏ることも、高血圧症などの生活習慣病のリスクを高めます。
コーヒーと高血圧の関係
 コーヒーの血圧への影響については、これまでさまざまな研究が行われています。
コーヒーの血圧への影響については、これまでさまざまな研究が行われています。
コーヒーを飲むことで一時的に血圧が高くなることはあるものの、その習慣が高血圧症の発症に影響することはない、というのが現在の一般的な見解です。
ただ、砂糖入りのコーヒーについては、高血圧症・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病のリスクを高めるおそれがあります。コーヒーがお好きな方は、ドリップして淹れるブラックコーヒー、または少量のミルクを入れた砂糖なしのコーヒーを飲むことをおすすめします。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員