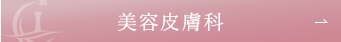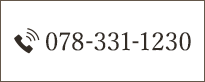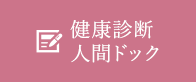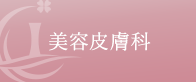出口で詰まる便・便秘の
症状はご相談ください

- 3日以上排便がない
- 1~2日に1回排便があるが、便が硬い
- 排便後、便が残っている感じがする(残便感)
- 便が硬く、排便時に痛みを感じる
- 便がウサギのフンのようにコロコロしている
- 腹痛が続いている
- 膨満感が続いている
- 便秘薬を使う回数が増えた、効かなくなってきた
特に注意が必要な便秘の症状
- 4日以上排便がない
- 血便や下血がある
- 粘血便が出た
- 便秘と下痢が交互にある
- 強い腹痛が続いている
- 便が細くなった
- 吐き気・嘔吐・発熱がある
便秘の種類と主な原因
直腸性便秘
直腸までは便がスムーズに通過してきたものの、直腸が反応しないために排便に至らないタイプの便秘です。
便意を感じた時にすぐにトイレに行くことが難しい仕事をしている方、寝たきりの方などによく見られます。排便を我慢することを繰り返しているうちに、便が到達しても直腸が正しく反応しなくなります。
弛緩性便秘
腸管の蠕動運動、便の水分を吸収する機能に異常があるために便が硬くなるタイプです。
加齢、食物繊維・水分の不足、下剤の長期服用などが原因として挙げられます。
けいれん性便秘
胃や腸などの働きを支配する、自律神経のバランスが乱れることで起こる便秘です。
原因としては、ストレスや睡眠不足、生活リズムの乱れなどが挙げられます。
便秘の原因となる病気
便秘は「体質」と捉えられがちな症状です。しかし、以下のようなさまざまな病気によって引き起こされることが少なくありません。
便秘のときの検査
 問診では、便の状態(色・形・血液の付着の有無など)、その他の症状、生活習慣、既往歴・家族歴、服夜中の薬などについてお尋ねします。
問診では、便の状態(色・形・血液の付着の有無など)、その他の症状、生活習慣、既往歴・家族歴、服夜中の薬などについてお尋ねします。
その上で、糖尿病や甲状腺機能低下症などが疑われる場合には血液検査を、大腸の病気が疑われる場合には大腸カメラ検査を行います。その他、腸管の便やガスの状態を調べるためにレントゲン検査を行うこともあります。
当クリニックでは、内視鏡の専門医・指導医が大腸カメラ検査を行います。鎮静剤を使用し、ほとんど苦痛なく大腸カメラ検査を受けられますので、安心してご相談ください。
便秘の治療
便秘の原因となる疾患が見つかった場合には、その疾患に対する治療を行い、症状の改善を図ります。
原因疾患がない場合には、以下のような治療を行います。
生活習慣の見直し
 食事療法としては、水分・食物繊維を意識的に摂るようにし、栄養バランスも維持します。
食事療法としては、水分・食物繊維を意識的に摂るようにし、栄養バランスも維持します。
運動療法では、腸を刺激する適度な運動について指導します。ウォーキングや軽いジョギングの他、ヨガやストレッチも良いでしょう。
また排便習慣の改善も大切です。毎朝決まった時間にトイレに行く、スマホを触るなどして長く便座に座らない、便意を感じたら我慢せずすぐにトイレに行くといった習慣により、正しい排便を促します。
薬物療法
患者様のお身体の状態やライフスタイルに応じて、下剤を処方します。ほとんどのケースで十分な効果が得られますが、下剤をやめられるよう、並行して生活習慣の改善にもしっかりと取り組みましょう。
自力で便秘解消法のポイント

生活リズムを整える
起床時間や就寝時間がバラバラ、食事の回数・時間が日によって異なるといった場合には、まずは生活リズムを整えましょう。生活リズムを整えることで、毎日決まった時間に便意が訪れやすくなります。
決まった時間にトイレに行く
便意がなくても、朝食後などの決まった時間にトイレに行く習慣を身につけましょう。最初は出ないまま終わるかもしれませんが、継続していくうちに排便のリズムが一定になることが期待できます。
便意を感じた時は
すぐにトイレに行く
排便を我慢する習慣があると、直腸の反応が鈍くなり、便秘になることがあります(直腸性便秘)。便意を感じたら、我慢せずトイレに行く癖をつけましょう。
水分・食物繊維を
意識して摂取する
水分、食物繊維を意識的に多めに摂りましょう。食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく摂ることが大切です。特に、起床後のコップ一杯の飲水は、腸を刺激し排便を促す効果が期待できます。
ビフィズス菌・オリゴ糖を
意識して摂取する
腸内環境を整える「ビフィズス菌」、ビフィズス菌を増やす・悪玉菌の働きを抑える「オリゴ糖」を摂るのもおすすめです。ビフィズス菌はヨーグルト・キムチなどの発酵食品に、オリゴ糖は大豆・玉ねぎ・ごぼうなどに、それぞれ多く含まれます。
脂質も適度に摂る
「太る」「不健康」というイメージのある脂質ですが、炭水化物・タンパク質とともに重要な栄養素です(三大栄養素)。脂質には、腸内での便の滑りを良くする効果があります。極端に減らすことはせず、適度に摂取してください。
適度な運動をする
ウォーキング、軽いジョギング、ヨガ、ストレッチなどの運動によって、腸が刺激され、排便が促されます。便秘の解消においては、負荷が軽かったり時間が短くてもいいので、毎日運動を継続することに重点を置いてください。
ストレスが
溜まる前に解消する
ストレスは自律神経のバランスを乱し、便秘などの胃腸の症状の原因になります。毎日のリラックスタイム、休日の趣味・スポーツなどで、ストレスが溜まる前に小まめに解消するようにしましょう。
お腹のマッサージをする
おへそを中心に「の」の字を描くように優しくマッサージをすると、腸を刺激したり、便の移動を助けたりといった効果が期待できます。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員