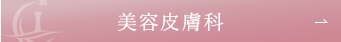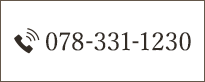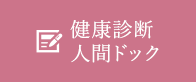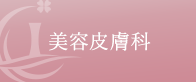- アニサキスは加熱して食べたら問題ない!?
- アニサキス症の症状
- アニサキス症の原因となる魚介類
- アニサキス症の検査・診断
- アニサキス症の治療
- アニサキス症予防の効果的な方法
- アニサキスにお酢は効果的?
養殖魚にはいない?
アニサキスは加熱して
食べたら問題ない!?
アニサキスとは
 アニサキスとは、幅0.5~1mm、長さ20~30mmの、糸状の寄生虫です。サバ、アジ、イワシ、以下など、アニサキスが寄生した魚介類を食べることで、人に感染します。
アニサキスとは、幅0.5~1mm、長さ20~30mmの、糸状の寄生虫です。サバ、アジ、イワシ、以下など、アニサキスが寄生した魚介類を食べることで、人に感染します。
アニサキスは人の体内では1週間ほどしか生きられませんが、感染時には強い腹痛、吐き気・嘔吐、発熱などの症状を引き起こします。一方で、まったくの無症状のままアニサキスが死に、排泄されるということもあります。
アニサキスは、内視鏡による摘出が可能です。魚介類を食べ、強い腹痛などの症状が現れた場合には、緊急での内視鏡検査・摘出を行います。
※内視鏡検査の準備をしますので、ご来院前に一度、お電話でお問合せください。
アニサキス症を防ぐために
アニサキスへの感染によって、胃腸などで症状をきたした状態を「アニサキス症」と言います。
魚介類を食べる時には、60~70℃での1分以上の加熱、またはマイナス20℃以下で24時間冷凍することで、アニサキスを死滅させることができます。
ただ、現実的に100%、アニサキス症を予防することは困難です。また、アニサキス自体がアレルゲンとなるアニサキスアレルギーでは、死滅したアニサキスが体内に入っただけで、蕁麻疹などの症状が現れます。
アニサキス症の症状
胃アニサキス症
アニサキスが寄生した魚介類を食べた数時間~十数時間後、胃の激しい痛み、吐き気・嘔吐などの症状が現れます。胃痛は、一時的に引き、再発を起こすということが繰り返されます。
胃カメラによる摘出が可能です。
腸アニサキス症
アニサキスが寄生した魚介類を食べた十数時間後~数日後、下腹部の激しい痛み、発熱、吐き気・嘔吐、頻脈などの症状が現れます。ごく稀に、腸閉塞、腸穿孔などを起こします。
消化管外アニサキス症
消化管から腹腔内へとアニサキスが飛び出てしまい、肉芽腫を形成します。肉芽腫の部位によって、さまざまな症状が引き起こされます。
アニサキスアレルギー
アニサキスに対するアレルギー反応として、蕁麻疹などの症状が現れることがあります。アニサキスアレルギーを持つ方の場合は、魚介類を十分な加熱または冷凍して、アニサキスが死んでいる場合でも症状が出ます。アナフィラキシーショックを起こし、危険な状態に陥ることもあります。
アニサキス症の
原因となる魚介類
アニサキス症は、アニサキスが寄生する魚介類を、十分な加熱または冷凍処理をせずに口にした場合に発症します。アニサキスが寄生しやすい魚介類と、寄生しにくい魚介類をご紹介します。
特にアニサキスが寄生しやすい魚介類を刺身などで食べる時、注意が必要です。
アニサキスが多く見られる魚介類・ほとんど見られない魚介類
アニサキスが多い魚介類
- サバ
- アジ
- イワシ
- イカ
- サンマ
- サケ
- タラ
- ホッケ
- イカ
- ホタルイカ
上記のような魚介類を食べる際には、以下のいずれかの方法によって、アニサキスを死滅させることが大切です。
- 60~70℃での1分以上の加熱
- マイナス20℃以下で24時間冷凍
※一般的な家庭用冷蔵庫では、マイナス18℃までしか下がりません。その場合は、48時間以上の冷凍が必要です。
アニサキスがほとんどいない魚介類
- 淡水魚
- ボラ
- トビウオ
- ホヤ
- ウニ
- ナマコ
- アナゴ
- ウツボ
- 貝類
- 甲殻類
上記のような魚介類については、アニサキスが寄生している可能性は低くなります。
アニサキス症の検査・診断
 問診では、症状、数日間の食事の内容などについてお伺いします。
問診では、症状、数日間の食事の内容などについてお伺いします。
その上で、胃にアニサキスがいると思われる場合には、胃カメラ検査を行います。アニサキスを発見次第、摘出します。当クリニックでは、内視鏡の専門医・指導医が、必要に応じて鎮静剤を使用し、苦痛の少ない胃カメラ検査を行っております。
胃以外にアニサキスがいると思われる場合には、レントゲン検査・超音波検査・血液検査などを行います。
アニサキス症の治療
胃カメラ検査によってアニサキスを発見した場合には、内視鏡の先端から鉗子を出し、その場で摘出します。摘出後、痛みなどの症状は速やかに改善します。
アニサキス症予防の
効果的な方法
アニサキス症を予防するためには、以下のような方法が有効です。
加熱
60~70℃での1分以上の加熱をすれば、アニサキスは死滅します。
冷凍処置
マイナス20℃以下で24時間冷凍することで、アニサキスは死滅します。ただし、一般的な家庭用冷蔵庫ではマイナス18℃までしか下げられませんので、その場合は、48時間以上、冷凍してください。
冷凍されたまま売られている魚、冷凍で輸送され解凍して売られている魚は、基本的にアニサキス症の心配はないと言われています。
目視での摘出
十分な加熱や冷凍ができない場合には、魚を調理する時、調理後口に運ぶ時に、目でアニサキスの有無を確認しましょう。アニサキスは、幅0.5~1mm、長さ20~30mmの糸状の、半透明~白色の寄生虫です。
よく噛んで食べる
よく噛むことで、アニサキスを死滅させるという方法です。アニサキスを噛んでいるかもしれないと考えるのは気持ちの良いものではありませんが、感染予防としては有効です。
アニサキスにお酢は効果的?
養殖魚にはいない?
アニサキスについて、間違った情報も出回っているようです。
誤った対応で感染したり、不要な心配をしたりしないよう、ご注意ください。
アニサキスは酢・塩・
ワサビでは死滅しません
酢や塩、ワサビを使ったからといって、アニサキスが死ぬということはありません。
〆サバ、アンチョビ、ワサビ入り握りずしなども、アニサキスが潜んでいる可能性があります。
養殖魚にもアニサキスが
寄生していることがあります
養殖魚は、天然魚と比べるとアニサキスが寄生している割合が低くなると言われています。
ただ、養殖だから100%アニサキスが寄生していない、食べても感染しないということはありません。感染予防のためには、天然魚と同じように加熱や冷凍をすることが大切です。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員