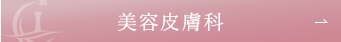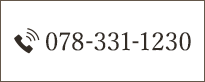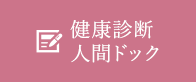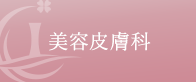お腹が張る・膨満感の症状は
ご相談ください
 お腹の張り・膨満感といった症状は、早食いによって飲み込んだ空気、食べ過ぎ、便秘など、さまざまな原因により引き起こされます。一時的であり、食事から時間が経つにつれて解消されるようでしたら、過度な心配はいりません(ただし早食い・食べ過ぎなどは繰り返さないようにしましょう)。
お腹の張り・膨満感といった症状は、早食いによって飲み込んだ空気、食べ過ぎ、便秘など、さまざまな原因により引き起こされます。一時的であり、食事から時間が経つにつれて解消されるようでしたら、過度な心配はいりません(ただし早食い・食べ過ぎなどは繰り返さないようにしましょう)。
一方で、便秘や胃腸の病気を原因としている場合には、治療が必要です。お腹の張り・膨満感が続く、食べ過ぎでもないのに症状が繰り返される、食欲不振・腹痛・むくみ・発熱などの症状を伴うといった場合には、お早目に当クリニックにご相談ください。
膨満感の原因・メカニズム
膨満感の原因は、
消化管に溜まったガス
人は誰でも、食事をすると消化管でガスが発生します。ガスはゲップなどの呼気、おならとして対外へと排出されます。ガスの発生量が多かったり、排出がうまくいかなかったりする場合に、膨満感が生じます。
ガスの量が多くなる原因
自律神経のバランスの乱れ
ストレスなどを原因として自律神経のバランスが乱れると、消化管でのガスの量が多くなることがあります。呑気症では、無意識に空気を多く飲み込んでしまいます。またストレスが機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群を引き起こし、膨満感を伴うこともあります。
腸内細菌叢のバランスの乱れ
食生活などの乱れによって腸内で悪玉菌が増加すると、異常発酵によってガスが多量に産生されます。腸内細菌叢のバランスの乱れは、炎症性腸疾患など大腸の病気のリスクを高めるものと考えられます。
ガスの排出が
うまくいかない原因
ガスの排出が妨げられる原因としては、便秘、過敏性腸症候群、腸閉塞などが挙げられます。
膨満感を伴う病気
膨満感は、胃腸の病気でよく見られる症状です。
腸閉塞
腹部手術や腹膜炎などによる腸管の癒着、腸管の蠕動運動の低下、血流障害などを原因として腸管が部分的に狭くなり、便がうまく通過しない状態です。膨満感の他に腹痛や嘔吐、便秘、発熱などの症状が見られます。早急な治療が必要です。
呑気症
ストレスなどによって、空気をたくさん飲み込んでしまう病気です。消化管内でのガスとなり、膨満感を引き起こします。ゲップ・おならが増えるという症状を伴うこともあります
逆流性食道炎
加齢による下部食道括約筋の緩み、肥満による腹圧の上昇、暴飲暴食による胃酸の分泌過多などを原因として、胃液が繰り返し逆流して食道粘膜を傷つける病気です。胸やけ、呑酸、ゲップ、のどの痛み、膨満感などが見られます。
急性胃腸炎
ウイルス・細菌の感染、薬の副作用、暴飲暴食などを原因として起こる胃腸炎です。吐き気・嘔吐、膨満感、腹痛、下痢、発熱などの症状を伴います。細菌性の胃腸炎の場合には、血便が見られることもあります。
機能性ディスペプシア
胃の粘膜に炎症などの異常が認められないにもかかわらず、胃やみぞおちの痛み、不快感、膨満感などの症状が慢性化する病気です。発症には、ストレスが影響しているものと考えられます。
腹部の腫瘍
胃がん・大腸がん・すい臓がん・卵巣がんなどの腫瘍によって、膨満感が引き起こされることがあります。
上腸間膜動脈症候群
大動脈と上腸間膜動脈に挟まれた部分には、クッションの役割を果たす脂肪があります。無理なダイエットなどによってこの脂肪が減少すると、食後の胃もたれ、腹痛、膨満感、吐き気・嘔吐などを伴う上腸間膜動脈症候群を発症することがあります。
膨満感のときの検査
 問診では、症状や食習慣、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお尋ねします。またお腹の触診・聴診なども行います。
問診では、症状や食習慣、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお尋ねします。またお腹の触診・聴診なども行います。
その結果に応じて、レントゲン検査、超音波検査、胃カメラ検査、大腸カメラ検査などを行い、診断します。当クリニックの院長は、内視鏡の専門医・指導医です。確実性と安全性の高い内視鏡検査を行いますので、安心してご相談ください。鎮静剤を使用し、ほとんど苦痛を感じることなく、内視鏡検査を受けていただけます。
お腹の張りが
気になるときの対処法
生活習慣の改善
 食事においては、食べ過ぎ・早食い、アルコールや刺激物の摂り過ぎ、栄養の偏りなどがあれば、改善のための指導を行います。発酵食品などによって、腸内細菌叢のバランスを整えるのも有効です。
食事においては、食べ過ぎ・早食い、アルコールや刺激物の摂り過ぎ、栄養の偏りなどがあれば、改善のための指導を行います。発酵食品などによって、腸内細菌叢のバランスを整えるのも有効です。
腸を刺激しその働き・便通を改善する適度な運動にも取り組みましょう。
ストレスの解消
ストレスなどによって自律神経のバランスが乱れると、胃腸の働きが低下し、膨満感などの不快な症状の原因となります。またストレスは、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群の原因やリスク因子となります。
ストレスを溜め込まないこと、溜まる前に小まめに解消することで、症状の改善を図ります。
長引く膨満感は早めの受診を
 冒頭で申し上げた通り、食後に少しお腹が張るものの、その後時間の経過と共に解消されるようでしたら、基本的に心配はいりません。
冒頭で申し上げた通り、食後に少しお腹が張るものの、その後時間の経過と共に解消されるようでしたら、基本的に心配はいりません。
しかし、膨満感が続いている、食べ過ぎたわけでもないのに繰り返される、食欲不振・腹痛など他にも症状があるといった場合には、何らかの病気を疑い、当クリニックにご相談ください。病気を原因としない場合でも、生活習慣の改善指導を行うことで、症状の改善を図ります。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員