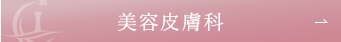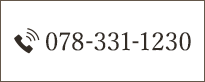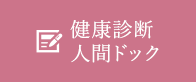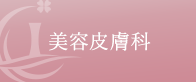急性胃粘膜病変 (急性胃炎)
急性胃粘膜病変
(急性胃炎)とは
突発する上腹部痛,吐き気,嘔吐,時に吐血・下血の症状を伴って発症し,この際早期に内視鏡で観察すると,胃粘膜面に明らかな炎症性変化,出血,潰瘍性変化(びらん,潰瘍)が観察されるもの”と定義されています。
急性胃炎の症状
 急性胃炎では、主に以下のような症状が見られます。
急性胃炎では、主に以下のような症状が見られます。
- 胃の痛み
- 胸やけ
- 吐き気
- 胃のむかつき
- 胃の重い感じ
- 食欲不振
- お腹の張り
急性胃炎の原因
食べ過ぎ・お酒の飲み過ぎ・刺激物の摂り過ぎなど、暴飲暴食が原因になることが多くなります。
その他、感染症・食中毒、ストレス、非ステロイド系消炎鎮痛剤の副作用などが原因になることもあります。
急性胃炎の検査
 まずは丁寧に問診を行います。問診では、症状、思い当たる原因、既往歴、服用中の薬などについてお伺いします。その上で、必要に応じて胃カメラ検査を行います。
まずは丁寧に問診を行います。問診では、症状、思い当たる原因、既往歴、服用中の薬などについてお伺いします。その上で、必要に応じて胃カメラ検査を行います。
胃カメラ(上部消化管内視鏡)では、胃の下部(前庭部)を中心に、出血した血液が固まった「凝血塊(ぎょうけつかい)」が付着した浅い潰瘍が多く見られるのが特徴です。中には、出血が続く可能性のある潰瘍(動脈性出血のリスクを伴うもの)が見つかることもあり、その場合は内視鏡を使って止血処置(内視鏡的止血術)を行うことが必要になります。また、十二指腸にも同様の病変が見られることもあります。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)
慢性胃炎(萎縮性胃炎)とは
「慢性胃炎」なかには、いくつかのタイプがあります。内視鏡(胃カメラ)で見ると、びらん性胃炎(粘膜がただれている状態)、表層性胃炎(表面だけに炎症がある状態)、そして萎縮性胃炎(胃の粘膜がうすく弱くなっている状態)などが含まれます。
その中でも、「慢性胃炎」と言った場合には、ピロリ菌感染が原因となる萎縮性胃炎を指すことが一般的です。
慢性胃炎
(萎縮性胃炎)の症状
 萎縮性胃炎は、初期にはほとんど症状がないことも多いですが、次のような症状が出ることもあります。
萎縮性胃炎は、初期にはほとんど症状がないことも多いですが、次のような症状が出ることもあります。
- 胃の痛み
- 夜間や空腹時の胸やけ
- 吐き気
- 胃のむかつき
- 胃の重い感じ
- 食欲不振
- お腹の張り
慢性胃炎
(萎縮性胃炎)の原因
慢性胃炎のうち、約8割がピロリ菌感染を原因として発症します。ピロリ菌の感染は幼少期(4-5歳くらいまで)起こります。以前は井戸水などを介した感染が主でしたが、近年では親から子への口移しなどを通じた感染が増えています。そのため、両親にピロリ菌感染がある場合は注意が必要です。
その他、ストレス、非ステロイド系消炎鎮痛剤の副作用、日常的なお酒の飲み過ぎなどが原因になることもあります。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)を
放置するとがん化!?
ピロリ菌は、子どものころに感染することが多く、最初は胃の出口あたりにある部分に住みつき、胃に炎症を起こします。その後、だんだんと胃の上の方へ広がっていきます。
ピロリ菌は、胃の中でも特に粘膜がうすくて、胃酸が少ない場所に感染しやすく、時間がたつと胃全体に炎症を引き起こすようになります。
この炎症が長く続くと、胃の粘膜がだんだんと薄くなっていきます。この状態を「萎縮性胃炎(いしゅくせいいえん)」と呼びます。さらに進むと、胃の粘膜が腸のような性質に変わってしまう「腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)」という変化が起こります。
一度このような変化が起こった胃の粘膜は、たとえピロリ菌を除菌しても、元の健康な状態には戻りません。そして、この腸上皮化生が起きた粘膜からは、胃がんが発生しやすくなることがわかっています。
そのため、ピロリ菌の除菌はできるだけ早く行うことが大切です。また、除菌治療がうまくいった後も、胃がんの予防のために、定期的に胃カメラ(内視鏡)検査を受けることが必要です。
慢性胃炎
(萎縮性胃炎)の検査
 胃カメラの検査で「慢性胃炎(萎縮性胃炎)」が疑われた場合は、まず血液検査や息を取る検査でピロリ菌に感染しているかどうかを調べます。検査の結果、ピロリ菌の感染が確認された場合は、除菌治療を行います。
胃カメラの検査で「慢性胃炎(萎縮性胃炎)」が疑われた場合は、まず血液検査や息を取る検査でピロリ菌に感染しているかどうかを調べます。検査の結果、ピロリ菌の感染が確認された場合は、除菌治療を行います。
一方で、ピロリ菌が原因ではないと判断された場合には、他の原因に応じた適切な治療を行っていきます。
治療や治し方
急性胃炎、慢性胃炎と診断した場合には、主に以下のような治療を行います。
薬物療法
 対症療法として、胃粘膜を保護する薬、胃酸の分泌を抑制する薬などを内服します。
対症療法として、胃粘膜を保護する薬、胃酸の分泌を抑制する薬などを内服します。
ただし、これらは根本的な治療ではないため、あわせて生活習慣の改善、ピロリ菌検査が陽性だった場合の除菌治療を行うことが大切です。
生活習慣の改善指導
食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、刺激物の摂り過ぎなどを控え、消化の良いものを摂ります。症状の改善具合を見ながら食事を元に戻しますが、再発防止のため、食生活の乱れがないように指導いたします。なお急性胃炎の場合には、絶食が必要になることもあります。
十分な睡眠をとること、規則正しい生活を送ることも大切です。
胃炎についてよくある質問
急性胃炎は、自力で治すことも
できますか?
食生活の乱れを原因としている場合には、食習慣を改善し、胃を休めれば多くは数日で改善します。ただ、感染症・食中毒、ストレス、非ステロイド系消炎鎮痛剤の副作用などが原因になることもあります。急性胃炎だと思っていたら胃潰瘍だったということもあるため、やはり医療機関を受診するのが安心です。
慢性胃炎を放置していると、
どうなりますか?
慢性的な炎症は胃粘膜を萎縮させるため、萎縮性胃炎への進行が懸念されます。また萎縮性胃炎の一部は、胃がんの原因となります。慢性胃炎を早期発見・早期治療することが、胃がんのリスクを下げることにつながります。症状が軽くても甘く見ず、必ず当クリニックにご相談ください。
胃の痛みがどれくらい続けば、
受診すべきでしょうか?
すぐにご相談いただくのがベストですが、一般的には1週間くらいが目安となります。市販の胃薬で症状が抑えられている場合も、1週間が経過しても手放せない(飲み続けなければ痛みが引かない)場合は必ず受診してください。
「刺激物の摂り過ぎ」とは、
具体的にどういったことでしょうか?
香辛料の入った辛い食べ物、アルコール全般、コーヒーや紅茶などのカフェイン入り飲料、炭酸などが挙げられます。胃の症状が出た時はもちろんですが、普段から摂り過ぎないように注意しましょう。
ピロリ菌検査で陽性だった場合、
必ず除菌治療を受けなければなりませんか?
ピロリ菌は、慢性胃炎(萎縮性胃炎)だけでなく、胃がん、胃・十二指腸潰瘍などの原因となります。薬物療法・生活習慣の改善などで症状が改善できたとしても、ピロリ菌に感染したままでは根本的な治療になりません。ピロリ菌検査で陽性だった場合は、必ず除菌治療を受けましょう。
慢性胃炎を放置した場合、
どれくらいの確率で胃がんになりますか?
慢性胃炎を放置して胃がんになる確率について、はっきりした数字は分かっていません。胃炎の重症度、ピロリ菌感染の有無、年齢、生活習慣などによって変動するためです。しかしながら、除菌に成功した場合(除菌成功群)と除菌に不成功であった場合(除菌不成功群)の長期成績では、除菌成功群では、不成功群の39%まで胃がん発生を減少させたことが報告されています。慢性胃炎と診断された時には、速やかに適切な治療を受けましょう。またその後は、定期的に胃カメラ検査を受けることをおすすめします。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員