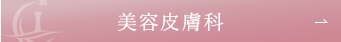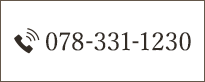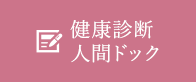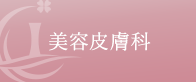クローン病とは
 クローン病は潰瘍性大腸炎と共に、原因不明の炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)に分類される病気です。大腸・小腸を中心とした口~肛門までの消化管で、慢性的な炎症が起こります。大腸のみに炎症が留まる潰瘍性大腸炎とは区別して治療する必要があります。クローン病では、腹痛、下痢、体重減少、血便、発熱、貧血、倦怠感といった症状が見られます。
クローン病は潰瘍性大腸炎と共に、原因不明の炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)に分類される病気です。大腸・小腸を中心とした口~肛門までの消化管で、慢性的な炎症が起こります。大腸のみに炎症が留まる潰瘍性大腸炎とは区別して治療する必要があります。クローン病では、腹痛、下痢、体重減少、血便、発熱、貧血、倦怠感といった症状が見られます。
クローン病の症状と
合併症について
クローン病の症状と
合併症について
クローン病の症状は患者様一人ひとりで異なり、さらに病変が生じている部位(大腸型・小腸型・小腸大腸型)によっても異なります。
主な症状
 もっとも特徴的な症状は「腹痛」と「下痢」で、患者様の半数以上にみられます。
もっとも特徴的な症状は「腹痛」と「下痢」で、患者様の半数以上にみられます。
そのほかにも、以下のような全身的な症状が現れることがあります。
- 発熱
- 血便・下血
- 体重の減少
- 全身倦怠感(強い疲労感)
- 貧血
これらの症状は、病状の進行や活動性によって変化するため、定期的な経過観察が重要です。
腸管の合併症
クローン病では、腸の慢性的な炎症により、以下のような腸管の合併症がみられることがあります。
- 瘻孔(ろうこう):腸と他の臓器または皮膚との間にできる異常な通路
- 狭窄(きょうさく):腸の一部が狭くなることにより、通過障害を引き起こす状態
- 膿瘍(のうよう):炎症が進行して膿がたまった状態
これらの合併症は、腹痛や発熱の原因となることもあり、早期の発見と治療が求められます。
腸管外の合併症
クローン病は腸以外の部位にも炎症が及ぶことがあり、以下のような「腸管外合併症」がみられることもあります。
- 関節炎(関節の腫れや痛み)
- ブドウ膜炎(眼に炎症が起きる病気)
- 結節性紅斑(けっせつせいこうはん):皮膚に赤く腫れたしこりができる炎症性疾患
- 肛門部病変(痔ろう、裂肛、肛門周囲膿瘍など)
これらの合併症の有無や程度によって、患者様の生活の質(QOL)に大きな影響を与える場合があります。
クローン病の診断と流れ
クローン病が疑われる場合、まず患者様から症状や病歴を詳しくお伺いし、そのうえで必要な検査を行って診断を進めていきます。
血液検査
 血液検査では以下の項目を中心に評価します。
血液検査では以下の項目を中心に評価します。
- 貧血の有無
- 体内の炎症反応
- 栄養状態の評価(アルブミンなど)
クローン病は他の疾患と似た症状を呈するため、除外診断(他の病気でないことを確認する)も重要です。そのため、便の培養検査や寄生虫検査などが必要になる場合があります。
大腸カメラ
(大腸内視鏡検査)
 次に、大腸カメラを用いて腸の内部を直接観察します。
次に、大腸カメラを用いて腸の内部を直接観察します。
この検査では
- クローン病に特徴的な病変の有無
- 炎症の分布範囲や程度
- 粘膜の状態を詳しく観察
さらに、必要に応じて生検(腸の粘膜を一部採取)を行い、病理組織学的に検査します。
総合的な診断
大腸カメラの所見、生検の結果、そして患者様の症状(例:血便・粘液便・腹痛など)を総合的に評価し、診断を行います。
その他の検査
必要に応じて、以下の検査を追加で行うことがあります。
- 胃カメラ検査:上部消化管の病変を確認
- 腹部超音波検査:腸管の状態を画像で確認
- CT検査・MRI検査:腸の周囲や深部の炎症の把握
- カプセル内視鏡検査・バルーン内視鏡検査:小腸の詳しい観察を目的とした検査
クローン病の治療
薬物療法
 薬物によって腸管の炎症を抑えることを目的とした治療です。これは、潰瘍性大腸炎の治療とも共通点が多く、病状の程度や経過に応じて適切な薬剤を選択します。
薬物によって腸管の炎症を抑えることを目的とした治療です。これは、潰瘍性大腸炎の治療とも共通点が多く、病状の程度や経過に応じて適切な薬剤を選択します。
主に使用される薬剤には以下のようなものがあります。
- 5-ASA(5-アミノサリチル酸)製剤:軽度から中等度の炎症に使用されます
- ステロイド:炎症が強い場合に短期間使用されることが多い薬剤です
- 血球成分除去療法(G-CAP):炎症を引き起こす白血球を体外で除去する治療法
- 生物学的製剤(インフリキシマブ、アダリムマブ、ウステキヌマブなど):重症例や再発を繰り返す場合に使用され、炎症に関わる特定の分子を標的にする先進的な治療です
栄養療法
クローン病の炎症を抑えるために、成分栄養剤(例:エレンタール)を使用した経腸栄養が行われることがあります。これは「食事療法」ではなく、腸をできるだけ安静に保ちつつ必要な栄養を補う治療法です。
重症の場合は、腸を完全に休ませるために完全静脈栄養(TPN)を行い、一時的に絶食となることもあります。
外科的治療(手術)
薬や栄養療法でコントロールできない合併症が生じた場合には、外科的治療が必要となることがあります。
手術が検討される主なケースは
- 腸閉塞
- 大量出血
- 瘻孔(腸に穴が開くこと)
- 膿瘍の形成
また、腸の狭窄が原因で食物が通過しにくくなった場合には、最近ではバルーン拡張術(小腸内視鏡を使用)が積極的に行われるようになっています。これは、手術を回避または延期する選択肢として有用とされています。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員