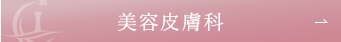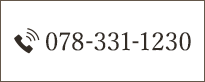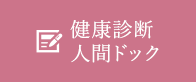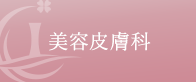ピロリ菌は
どのように感染するの?!
 ピロリ菌は、ピロリ菌に汚染された水・食品などを口にすることで感染(経口感染)すると考えられています。
ピロリ菌は、ピロリ菌に汚染された水・食品などを口にすることで感染(経口感染)すると考えられています。
なお、ピロリ菌は胃酸の酸性度が十分でない・免疫が未発達である5歳くらいまでに感染するもので、それ以降の胃での感染は成立しないと言われています。ただ、幼少期に感染した場合には、除菌治療を行わない限り感染が持続するため、注意が必要です。
家庭内での感染
主に、離乳食などの親子間の口移し、親が使った箸・スプーンなどで子どもに食べさせることなどで感染するものと思われます。現在の国内でのピロリ菌感染は、ほとんどが家庭内での大人から子という形で起こっていると言われています。
不衛生な環境における感染
井戸水など、十分に衛生管理されていない水、あるいはそういった水で洗った食品などを口にすることで感染するケースです。現在、日本国内でのこういった感染はほとんどありませんが、幼少期に井戸水を使っていた方は、感染している可能性があります。
医療現場における感染
海外では、口腔に使用した器具の十分な殺菌・消毒がされていなかったために、ピロリ菌感染が広がったというケースが報告されています。現在の日本国内での衛生基準であれば、ほとんど起こりえない感染です。
ピロリ菌とは
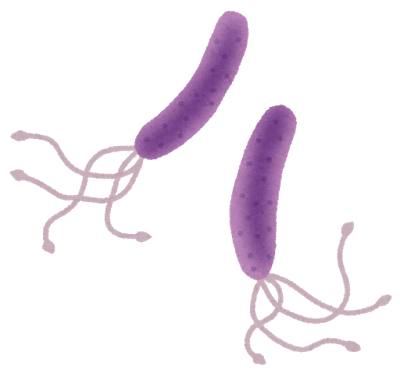 ピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)は、胃の粘膜に住みつく細菌です。
ピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)は、胃の粘膜に住みつく細菌です。
感染すると、胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなど胃の病気の原因やリスク因子となります。ピロリ菌は一度感染すると、除菌治療を行わない限り、その感染を持続させます。
上記の疾患に関する症状がすでに現れている方、ピロリ菌に感染しているかどうか気になる方は、お早目にご相談ください。
当クリニックでは、ピロリ菌の感染の有無を調べるピロリ菌検査、および除菌治療を行っております。
※保険では胃カメラを受けずにピロリ菌の検査を行うことはできません。ピロリ菌のみの検査は自費診療となります。
ピロリ菌感染を放置すると
胃がんになる!?
 長期にわたってピロリ菌感染を放置していると、まず慢性胃炎を発症します。その後、胃の粘膜が萎縮する萎縮性胃炎へと進行し、そのうちの一部が、胃がんの原因となります。
長期にわたってピロリ菌感染を放置していると、まず慢性胃炎を発症します。その後、胃の粘膜が萎縮する萎縮性胃炎へと進行し、そのうちの一部が、胃がんの原因となります。
胃がんの発症率は、ピロリ菌の感染によって約9倍、萎縮性胃炎を合併している場合は18~70倍にも達します。
注意が必要なのは、慢性胃炎や萎縮性胃炎、あるいは胃がんになっても、それほど症状が強く現れないことがあるという点です。ピロリ菌感染がある場合は除菌治療を行うことにより、胃がんの発生リスクを約1/3にまでへらせることが報告されています。特に胃がんのリスクが高くなる40歳以上の方は、定期的に胃カメラ検査を受けることをおすすめします。
ピロリ菌感染で
発症リスクが高まる病気
ピロリ菌に感染したままでいると、主に以下のような病気の発症リスクが高まります。
慢性胃炎・萎縮性胃炎
慢性胃炎は、ピロリ菌によって胃の粘膜が傷つき、炎症が長く続く病気です。この炎症が長期間続くと、やがて胃の粘膜がうすくなってしまい、「萎縮性胃炎(いしゅくせいいえん)」へと進行していきます。一度、粘膜にこのような変化が起こってしまうと、ピロリ菌を除菌しても、元の正常な状態には戻りません。そのため、粘膜の変化が進む前の段階で、できるだけ早くピロリ菌の除菌治療を行うことがとても大切です。
胃がん
ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜に変化が起こり、「萎縮性胃炎(いしゅくせいいえん)」という状態になります。このような変化がある粘膜からは、胃がんが発生しやすいことがわかっています。
また、ピロリ菌の除菌治療が成功した後でも、胃がんができる可能性(除菌後胃がん)は完全にはなくなりません。そのため、除菌後も安心せずに、定期的に胃カメラ(内視鏡)検査を受けて経過をしっかりと観察していくことが大切です。
胃MALTリンパ腫
胃の粘膜のリンパ組織(MALT)で生じる悪性腫瘍です。その約9割が、ピロリ菌感染を原因として発症すると言われています。
突発性血小板減少性紫斑病
血小板数が減少し、出血しやすくなる・出血が止まりにくくなる病気です。発症者の約6割が、ピロリ菌に感染していると言われています。
慢性じんましん
一部の慢性じんましんは、ピロリ菌感染を原因として発症します。強いミミズ腫れ、かゆみなどの症状を伴います。
ピロリ菌の検査・診断
ピロリ菌の検査は、胃カメラを使う方法と、使わない方法があります。
胃カメラ検査によって
行う検査
迅速ウレアーゼ検査
ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素によってアンモニアを作り出すことで、胃酸から身を守っています。
迅速ウレアーゼ検査では、胃カメラ検査で採取した組織を使い、ウレアーゼの活性を確認することで、ピロリ菌の感染を判定します。
短時間で結果が出ますが、除菌治療の判定(除菌できたかどうかの判定)には使用できません。
鏡検法
胃カメラで採取した組織をホルマリンで固定し、顕微鏡でピロリ菌の有無をチェックします。
診断の精度は、やや低くなります。
培養法
胃カメラで採取した組織を培養し、ピロリ菌の有無をチェックします。
培養し判定結果が出るまで、1週間ほどかかります。
胃カメラ検査以外の検査方法
尿素呼気試験法
ピロリ菌が作り出すウレアーゼによって、尿素がアンモニアと二酸化炭素に分解される仕組みを利用した検査です。
尿素の含まれるお薬を飲む前と後でそれぞれ呼気を採取し、二酸化炭素を検出することで、ピロリ菌の感染を判定します。
精度が高く、お身体への負担の少ない検査です。除菌治療の判定にも利用できます。ただし、検査前の21時間の飲水、検査前の6時間の食事ができないという飲食の制限があります。
血中抗ピロリ菌抗体測定
採血を行い、血液中の抗ピロリ菌IgG抗体を調べる検査です。
除菌治療の判定には使用できません。
尿中抗ピロリ菌抗体測定
採尿し、尿中のピロリ菌への抗体を調べる検査です。
簡便でありお身体への負担もないため、ピロリ菌のスクリーニング検査として実施されることが多くなります。
便中ピロリ菌抗原測定
便中のピロリ菌の抗原を調べる検査です。
感染の有無を調べる場合、除菌判定を行う場合のいずれであっても、精度の高い検査となります。
注意点
保険診療としてピロリ菌の検査・治療を受ける場合には、治療前に胃がんが無いことを確認する必要があるため胃カメラ検査が必須となります。すでに胃がんがある状態では、ピロリ菌を除菌しても、そのがんを治すことはできません。ピロリ菌の除菌は、あくまでも将来の胃がん予防に効果があるものであり、現在あるがんに対する治療にはならないためです。
胃カメラを使用しないピロリ菌検査を行う場合には、自費診療扱いとなります。
ピロリ菌の除菌治療
まずは一次除菌を行い、8週間後に除菌の判定を行います。一次除菌に失敗した場合には、二次除菌へと進み、8週間後に再度除菌の判定を行います。
一次除菌で約80%、二次除菌までで約98%が、除菌に成功します。
※三次除菌以降は、自費診療扱いとなります。
一次除菌
胃酸分泌抑制薬を1種類、抗菌薬を2種類、計3錠を、1日に2回、連続7日間内服します。
8週間後、除菌の判定のためのピロリ菌検査を行います。
二次除菌
抗菌薬のうち1種類を変更し、計3錠を、1日に2回、連続7日間内服します。
8週間後、除菌の判定のためのピロリ菌検査を行います。
ピロリ菌感染のよくある質問
「家族がピロリ菌に感染している
場合、自分も感染している可能性が高い」と言われるのはなぜですか?
現在の日本国内のピロリ菌感染が、主に親から子への口移し・箸やスプーンの共用によって起こっているものと考えられるためです。ご両親のどちらかがピロリ菌検査で陽性となった場合には、その子どもも感染している可能性が高くなります。
ピロリ菌は、キスでうつりますか?
キスでピロリ菌がうつることはないとされています。またピロリ菌は主に5歳までに感染するものであり、それ以降は感染や定着はほとんど起こらないと考えられます。
なぜ、大人は感染しないので
しょうか?
ピロリ菌は、胃酸の酸性度が十分でない・免疫が未発達である5歳くらいまでに感染するものと考えられています。ただ、酸性度や免疫の状態には個人差がありますので、6歳以降や大人が絶対に感染しないとは言い切れません。
水道水をそのまま飲んでいますが、ピロリ菌の心配はありませんか?
現在、日本国内の水道水を飲んだからといって、ピロリ菌に感染する心配はないと言われています。ただ、絶対に感染しないとは言い切れません。煮沸をして飲むようにすれば、より安全性が高まるものと考えられます。
ピロリ菌に感染しても、自覚症状は
ないのでしょうか?
ピロリ菌に感染したからといって、たとえば風邪のようにすぐに症状が出ることは基本的にありません。ただ、胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどを発症した場合には、胃痛、胃の不快感などの胃を中心とした症状が現れます。とはいえ、慢性胃炎や胃がんなど、早期には自覚症状が乏しい病気もあるため、必ず症状が出るとも言い切れません。気になる場合は、症状の有無に関係なく、一度当クリニックにご相談ください。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員