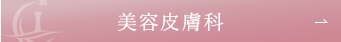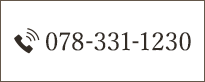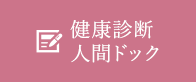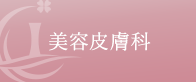糖尿病とは
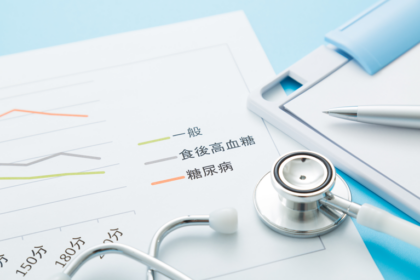 糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンの量が少ない、あるいはインスリンの働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖の濃度が高い状態(高血糖状態)が続く病気です。
糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンの量が少ない、あるいはインスリンの働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖の濃度が高い状態(高血糖状態)が続く病気です。
糖尿病は大きく、1型と2型に分けられます。食べ過ぎなどの生活習慣の乱れを原因とするのが2型糖尿病で、全体の95%以上を占めています。
糖尿病は症状に乏しい病気でありながら、進行すると神経障害・網膜症・腎症、心筋梗塞・脳卒中といった重大な合併症を招くリスクがあります。現在、40歳以上の3人に1人が糖尿病、または糖尿病予備軍であると言われています。
1型糖尿病と2型糖尿病
糖尿病は大きく、1型糖尿病と2型糖尿病に分けられます。「生活習慣病」の1つとなるのは2型糖尿病であり、こちらが糖尿病全体の95%以上を占めています。
1型糖尿病
先天的に膵臓でのインスリンの分泌が少ない、自己免疫疾患によって膵臓のβ細胞が破壊されるといったことを原因として発症する糖尿病です。主に、小児~青年期に発症します。
2型糖尿病と異なり、生活習慣の乱れは原因となりません。治療では、早期からインスリン療法を開始する必要があります。
2型糖尿病
生活習慣の乱れを主な原因として発症する糖尿病です。主に、中高年で発症します。
初期はほとんど自覚できる症状がありません。のどの渇き・多飲、多尿、疲労感、体重減少などの症状が現れた時には、ある程度進行しているものと考えられます。
治療では、食事療法・運動療法などによる生活習慣の改善が基本です。十分な効果が得られない場合には、薬物療法を導入します。
糖尿病の原因
1型糖尿病と2型糖尿病では、それぞれ原因が異なります。
1型糖尿病の場合
先天的な膵臓でのインスリン分泌能力の低さ、自己免疫疾患による膵臓のβ細胞の破壊などによって、インスリンがまったく、またはほとんど分泌されないことが原因となります。
ただ、なぜそのようなことが起こるのか、根本的な原因については解明されていません。
2型糖尿病の場合
食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、運動不足、肥満など、生活習慣の乱れが主な原因となります。膵臓でのインスリンの分泌量が低下する、または効きづらくなることで、糖尿病を発症します。
その他、遺伝、ストレスなども発症に影響すると言われています。
無症状で進行!?糖尿病の症状
糖尿病は、その初期症状の乏しさ、放置した場合の重大性から、「サイレントキラー」とも呼ばれます。
以下のような症状がすでに現れている場合には、糖尿病がある程度進行している疑いが強まります。お早目に当クリニックにご相談ください。
高血糖により引き起こす症状
- のどの渇き
- よく水を飲む
- 多尿、頻尿
- 疲労感
- 異常な空腹感、すぐにお腹が減る
- 十分な量を食べているのに体重が減る
合併症の症状
- 足のしびれ、痛み、むくみ
- 目のかすみ、視力低下
- 飛蚊症
- 息切れ、貧血
- 食欲不振
- 倦怠感
糖尿病は合併症が怖い‥
3大合併「しめじ」
糖尿病の3大合併症として、神経障害・網膜症・腎症があります。頭文字をとって「しめじ」と覚えます(め=目)。
いずれの合併症も動脈硬化が大きくかかわっており、進行すると深刻な事態を招きます。
神経障害
通常、最初に現れる合併症です。糖尿病になってから治療をせずにいると、平均して8年後に発症します。
糖尿病になると動脈硬化が進行しますが、これによりまずは足の神経が障害され、足の痺れや痛み、足裏に1枚紙が挟まっているような違和感、冷えなどが生じます。その後、同じような症状が手にも現れるようになります。
神経障害によって感覚が低下するため、暖房器具などの熱さに気づかず火傷を負うといったケースも見られます。
網膜症
通常、神経障害に次いで現れる合併症です。糖尿病になってから治療をせずにいると、平均して10年後に発症します。
動脈硬化によって目の網膜の血管が障害され、かすみ目、視力低下、まぶしさなどの症状が引き起こされます。網膜症を発症してからも放置していると、最悪の場合には失明に至ります。
糖尿病と診断されたら、定期的に眼科も受診しなくてはなりません。
腎症
通常、網膜症の次に現れる合併症です。糖尿病になってから治療をせずにいると、平均して15年後に発症します。
高血糖状態および動脈硬化が腎臓の血管を障害することで、血液を適切にろ過できなくなります。これにより、むくみ、高血圧、倦怠感などの症状が引き起こされます。
腎臓機能が大きく低下すると、人工透析が必要になります。
その他、動脈硬化によって狭心症や心筋梗塞、脳卒中などを合併することもあります。糖尿病を放置すると、健康やQOLを損なうだけでなく、命にかかわる疾患の発症リスクが高くなるのです。
糖尿病の検査・診断
問診
 問診では、主に以下のようなことをお尋ねします。
問診では、主に以下のようなことをお尋ねします。
- 症状
- 既往歴、家族歴
- 体重の変化
- 食習慣
- 運動習慣
- 飲酒や喫煙習慣の有無
- 服用中の薬(お薬手帳をお持ちください)
血液検査
 血液中のブドウ糖の濃度を示す「血糖値」と、「HbA1c」を測定します。
血液中のブドウ糖の濃度を示す「血糖値」と、「HbA1c」を測定します。
HbA1cは、過去1~2ヶ月の血糖値の状態が反映された平均の数値です。食事の影響を受けずに、血糖の状況を把握できます。
尿糖検査
尿に含まれるブドウ糖の量を調べる検査です。
糖尿病合併症検査
神経障害・網膜症・腎症、心筋梗塞・脳卒中などの合併症のリスクを把握するため、動脈硬化の程度を調べます。頚動脈の壁の厚みを調べる頚動脈超音波検査などがあります。
糖尿病の治療
糖尿病の診断後は、主に以下のような検査を行います。
治療の中心となるのは、食事療法と運動療法です。必要に応じて、薬物療法を導入します。
食事療法
その人に合った摂取カロリーを設定し、食べ過ぎを防ぎます。基本的に食事量を減らすことになりますが、栄養バランスが乱れないよう、当院の管理栄養士が指導いたします。基本的に「まったく食べられないもの」はなく、ストレスが溜まらないようなメニューを考えます。
お酒の飲み過ぎ、早食いなども控えましょう。
運動療法
ウォーキング、軽いジョギング、水泳などの有酸素運動と、レジスタンス運動(筋力トレーニング)を組み合わせた運動療法が有効です。筋力トレーニングといっても、器具を使用せず室内で行えるものが基本となります。
患者様の年齢、得意・不得意なども考慮し、継続しやすい運動療法を提案します。
薬物療法
 食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合には、薬物療法を導入します。
食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合には、薬物療法を導入します。
内服薬(経口血糖降下)
いくつかの種類がありますが、いずれも血糖値を下げる薬となります。ただ、その作用の機序はさまざまで、病態を考慮した上で適切なお薬を処方します。
インスリンの分泌を促進する薬、インスリンの作用を高める薬、糖の吸収や排泄をコントロールする薬などがあります。
GLP-1受容体作動薬
インスリンの分泌を促進し、血糖値を下げる作用のある薬剤です。
注射または内服により投与します。患者様のご希望、ライフスタイルに応じて選択します。
インスリン(注射)
血糖値を下げてくれるインスリンを、注射によって補います。
現在、作用の強さ、持続時間などが異なるさまざまなインスリン製剤が登場しています。患者様の病態、ライフスタイルに応じて選択します。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員