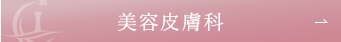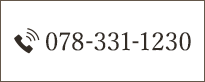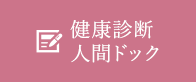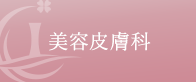胃がんとは
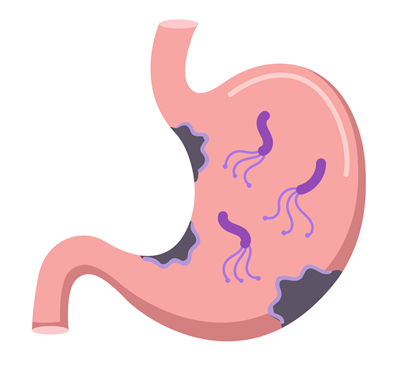 胃がんは、胃の粘膜から発生する悪性腫瘍(がん)です。胃がんにはいくつかの種類がありますが、がん細胞の形や性質によって「分化型」と「未分化型」に分けられます。分化型胃がんの多くはピロリ菌感染による慢性胃炎から発生することが多いとされています。一方で、未分化型胃がん(スキルス胃癌)はピロリ菌感染がない胃からも発生することがあります。未分化型胃がんは粘膜の表面ではなく、粘膜の下から発生するため発見が難しいとされています。現在、内視鏡治療の大きな進歩に伴い、早期発見することにより、従来の胃を切除する外科的治療ではなく内視鏡治療だけで根治できるようになりました。そのため、より一層早期で見つけることが重要です。
胃がんは、胃の粘膜から発生する悪性腫瘍(がん)です。胃がんにはいくつかの種類がありますが、がん細胞の形や性質によって「分化型」と「未分化型」に分けられます。分化型胃がんの多くはピロリ菌感染による慢性胃炎から発生することが多いとされています。一方で、未分化型胃がん(スキルス胃癌)はピロリ菌感染がない胃からも発生することがあります。未分化型胃がんは粘膜の表面ではなく、粘膜の下から発生するため発見が難しいとされています。現在、内視鏡治療の大きな進歩に伴い、早期発見することにより、従来の胃を切除する外科的治療ではなく内視鏡治療だけで根治できるようになりました。そのため、より一層早期で見つけることが重要です。
胃がんは、日本人に多いがんの一つです。
2021年の国立がん研究センターの統計によると、悪性腫瘍による死因として、男性で第3位、女性で第5位を占めています。
胃がんは、胃の内側を覆う「粘膜から発生する悪性腫瘍(がん)」です。がん細胞の形や性質によって、主に「分化型」と「未分化型」の2つのタイプに分類されます。
分化型胃がん
分化型胃がんは、がん細胞が本来の胃の粘膜の構造に似た性質をもつタイプで、多くはピロリ菌感染による慢性胃炎を背景に発生します。
胃の表層(粘膜表面)にできやすく、内視鏡検査で発見されやすいのが特徴です。
未分化型胃がん
(スキルス胃がん)
未分化型胃がん、特にスキルス胃がんは、がん細胞が正常な細胞とは異なる性質をもち、粘膜の下層から発生します。
このタイプはピロリ菌感染がない胃からも発生することがあり、表面から見えにくいため発見が難しいのが特徴です。
早期発見と治療の進歩
近年では、内視鏡技術の進歩により、早期の胃がんであれば胃を切除することなく、内視鏡だけで治療・根治できるケースが増えてきました。
そのため、胃がんをより早い段階で見つけることが非常に重要です。
何か気になる症状がある時はもちろんですが、無症状であっても40歳以上の方は、定期的に胃カメラ検査を受け、早期発見・早期治療に努めましょう。
胃がんの症状チェック
 胃がんは、命を危険にさらすことのある危険な病気でありながら、初期には症状が乏しいという特徴があります。
胃がんは、命を危険にさらすことのある危険な病気でありながら、初期には症状が乏しいという特徴があります。
以下のような症状に気づいた時には、放置せずお早目にご相談ください。
- 胃やみぞおちの痛み
- 胃のむかつき、不快感
- 食欲不振
- 胸やけ
- 吐き気
- 倦怠感
- 黒い便(タール便)
ピロリ菌感染を放置すると
胃がんになる!?
 ピロリ菌とは、胃の粘膜に棲みつく細菌です。主に、幼少期の親から子への口移しなどを原因として感染するものと考えられます。また、幼少期に井戸水など十分な衛生管理のなされていない水を飲み、感染したという方もいらっしゃいます。
ピロリ菌とは、胃の粘膜に棲みつく細菌です。主に、幼少期の親から子への口移しなどを原因として感染するものと考えられます。また、幼少期に井戸水など十分な衛生管理のなされていない水を飲み、感染したという方もいらっしゃいます。
ピロリ菌感染を放置していると、慢性胃炎・萎縮性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、そして胃がんの発症リスクが高まります。ピロリ菌検査を受け、陽性であった場合には、除菌治療を受けるようにしてください。一度ピロリ菌に感染すると、除菌治療を行わない限り感染が持続します。
胃がんの原因やなりやすい要因
胃がんは主に、以下のような原因によって発症します。
特に、ピロリ菌感染との強い関連性が指摘されています。
ピロリ菌感染
感染を放置することで、慢性胃炎・萎縮性胃炎を引き起こし、そのうちの一部は胃がんへと進行します。実際に、胃がん患者のほとんどにピロリ菌の感染が認められます。
塩分の摂り過ぎ
塩分の摂り過ぎは、胃がんの代表的な原因としてよく知られています。外食・できあいの弁当や総菜などで食事を済ませる人は、塩分摂取量が多くなりがちです。
喫煙
さまざまながんの原因となる喫煙ですが、胃がんとの関係も指摘されています。胃がん全体のうち、約20%が喫煙に起因して発症すると言われています。
家族歴
直接の原因ではありませんが、胃がんになった血縁者がいる場合、そうでない場合よりも胃がんの発症率が高くなることが分かっています。
胃がんの検査・診断
 問診では、症状、生活習慣、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお伺いします。
問診では、症状、生活習慣、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお伺いします。
その上で、胃カメラ検査を行い、食道・胃・十二指腸の粘膜を観察します。組織を採取する生検、確定診断のための病理検査も可能です。ピロリ菌の疑いがある場合は採血検査を行い、ピロリ菌感染の有無の確定診断を行います。
当クリニックでは、経験豊富な内視鏡の専門医・指導医が胃カメラ検査を行います。鎮静剤を使用した、ほとんど苦痛のない胃カメラ検査が提供しておりますので、安心してご相談ください。
胃がんの治療
内視鏡的治療
粘膜に留まる早期の胃がんであり、リンパ節転移の心配がほとんどない場合には、内視鏡を使った治療が可能です。外科治療(手術)と比べると、患者様のご負担が大幅に軽減されます。
内視鏡的粘膜下剥離術(ESD; Endo¬scopic Submucosal Dissection)
内視鏡を用い、病変の下に生理食塩水を注入して隆起させた上で、高周波ナイフを用いて病変を剥離・切除します。院長は開業するまでに500例以上の内視鏡治療(ESD)に携わってきました。治療が必要になった場合は、治療経験が豊富な専門施設をご紹介いたします。
外科治療
遠隔転移のない、手術での根治が期待できるケースで実施されます。
胃のすべてを摘出する術式、一部を摘出する術式などがあります。
監修 池澤伸明

- 2006年
関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年
順天堂大学医学部附属順天堂医院にて
臨床研修医 - 2008年-2009年
さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年
さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年
国立がん研究センター中央病院
消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年
明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年
神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員